「よーし、今日の試合は絶対勝つぞ!」
手に汗握りながら応援している、ひいきのチーム。時計は後半45分を指し、スコアは1-1の同点。90分間の死闘も、もう終わりか…。…と思ったら、ピッチの横で第4の審判員が掲げた電光掲示板には「5」の数字。
「え、まだ5分もやるの!?」
「なんで90分で終わらないの?」
「そもそもアディショナルタイムって何?ロスタイムとは違うの?」
サッカー観戦を始めたばかりの頃、誰もが一度は抱くこの素朴な疑問。あなたも今、まさにそう感じているかもしれませんね。ご安心ください。この記事を読み終える頃には、そのモヤモヤは興奮と納得に変わっています。
アディショナルタイムの「なぜ?」がわかれば、試合終了間際の数分間が、何倍も面白く、ドラマチックに見えてくるはずです。実は、その正体は試合中にプレーが止まっていた「消えた時間」を取り戻すための、極めて公平で、エキサイティングなルールなのです。
さあ、サッカー観戦が10倍楽しくなる秘密の扉を、一緒に開けていきましょう。
第1章:「90分で終わりじゃないの?」サッカーの時計が止まらない、不思議なルールの正体
試合中に生まれる「見えない時間」。これがアディショナルタイムが生まれる本当の理由だった!
まず、根本的な疑問から解決しましょう。
「なぜサッカーの試合は90分きっかりで終わらないのか?」。
その答えは、サッカー特有の時間の測り方である「ランニングタイム」にあります。野球やバスケットボールは、プレーが止まるたびに時計も止まりますよね。しかしサッカーでは、特別なケースを除き、前半45分・後半45分の間、審判の時計は基本的に止まりません。選手が倒れて治療を受けている間も、選手交代をしている間も、ゴールが決まって選手たちが喜んでいる間も、時間は刻一刻と進んでいきます。ここで問題になるのが、「プレーが止まっていた時間(=空費時間)」です。時計は進んでいるのに、ボールは動いていない。これでは、実際にプレーしている時間は90分よりも短くなってしまい、不公平ですよね。
この、試合中にいつの間にか生まれてしまった「消えた時間」を、試合の最後にきっちり追加して公平性を保つ。
これが、アディショナルタイムが存在する、たった一つのシンプルな理由なのです。
具体的に、どんな時に「消えた時間」は発生するのでしょうか?代表的な例を見てみましょう。
- 選手の交代選手の負傷によるプレーの中断や、治療のための時間
- 得点後のセレブレーション(ゴールパフォーマンス)
- VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)による判定の確認遅延行為(フリーキックやスローインをわざと遅らせるなど)
- その他、主審が「空費された」と判断した時間
これらの細かい「消えた時間」が積み重なり、アディショナルタイムとして試合の最後に加えられているのです。
第2章:「ロスタイム」はもう古い?「アディショナルタイム」が正式名称になったワケ
「失われた時間」から「加えられた時間」へ。呼び方が変わった、なるほどな理由
さて、ここで多くの方が疑問に思うのが「ロスタイム」という言葉との違いです。結論から言うと、現在、サッカーの競技規則で定められている正式名称は「アディショナルタイム」です。では、なぜ日本では今でも「ロスタイム」という言葉が広く使われているのでしょうか。
もともと「ロスタイム」は、英語の”Lost Time“(失われた時間)が由来です。意味合いとしては間違っておらず、長年日本のメディアやファンに親しまれてきたため、今でもその名残で使われています。しかし、サッカーのルールを定めるFIFA(国際サッカー連盟)は、このルールを”Additional Time“(追加された時間)と表現しています。
なぜ呼び方を変えたのでしょうか?そこには、言葉のニュアンスの違いがあります。
- Lost Time(ロスタイム):「失われた」という、どこかネガティブな響き。
- Additional Time(アディショナルタイム):「追加された」という、客観的で中立的な響き。
FIFAは、この時間を「失われたもの」ではなく、あくまで「プレーが止まった分を公平に追加するもの」と捉えています。そのため、世界基準の考え方に合わせて、より正確な表現である「アディショナルタイム」という言葉が公式に使われるようになったのです。ニュースや実況で解説者が「アディショナルタイム、いわゆるロスタイムですが…」と補足するのは、こうした背景があるからなんですね。
第3章:VARの導入でやたら長くなった?アディショナルタイムの計算、実はこんなに細かい
神の采配じゃない!アディショナルタイムの時間を決める明確なルールを徹底解説
「アディショナルタイムが5分になったり、時には10分以上になったりするのはなぜ?」その時間は、決して審判の感覚で決められているわけではありません。そこには、明確な計算のプロセスが存在します。
時間を決めるのは誰?電光掲示板に表示されるまでの流れ
アディショナルタイムの時間を計算し、表示するまでには、審判団の連携プレーがあります。
- 計算する人: 主に主審が、自身の時計で空費時間を計測・合算します。
- 伝える人: 主審が、第4の審判員(タッチライン際で交代などを管理する審判)に時間を伝えます。
- 表示する人: 第4の審判員が、電光掲示板にその時間を表示し、スタジアム全体に知らせます。
プロの計算式を大公開!アディショナルタイムの内訳
具体的に、どのような基準で計算されているのでしょうか。FIFAの競技規則で推奨されている目安は以下の通りです。
- 項目
- 選手の交代
- 得点後のセレブレーション
- VARの確認
- 選手の負傷対応
- 遅延行為など
例えば、後半に選手交代が合計5回(2分30秒)、ゴールが2つ(約2分)、VARの確認が1回(約1分30秒)あったとすれば、それだけで合計6分のアディショナルタイムが算出されるわけです。
カタールW杯で話題に!最近ATが長くなった2つの理由
2022年のカタールワールドカップでは、アディショナルタイムが10分を超える試合が続出し、話題になりました。これには2つの大きな理由があります。
- VARの導入: VARによる確認には数分かかることがあり、その中断時間が厳密にアディショナルタイムに加算されるようになったため。
- FIFAの方針転換: FIFAが「実際にボールが動いている時間(アクチュアル・プレーイングタイム)を最大限確保する」という方針を強く打ち出し、これまで曖昧にされがちだった細かい空費時間も、より正確に計測するよう審判に指示したため。
この流れは現在も続いており、アディショナルタイムは今後も長くなる傾向にあると言えるでしょう。
【初心者あるあるQ&A】表示時間より長くなるのはなぜ?
「電光掲示板に『5分』と表示されたのに、5分過ぎても試合が終わらない!」というケース、よくありますよね。
実は、掲示された時間は「最低限、追加される時間」を意味します。
もし、アディショナルタイムの5分間に、さらに選手の負傷や大きなプレー中断があれば、その分の時間がさらに追加されるのです。そのため、表示時間よりも試合が長くなることがある、と覚えておきましょう。
第4章:最後の1秒まで見逃せない!アディショナルタイムが生んだ奇跡の逆転劇
この数分のためにチケット代を払う価値あり!伝説のアディショナルタイム劇場へようこそ
ルールを理解すると、アディショナルタイムがいかに重要で、ドラマチックな時間かがわかってきます。この「魔の時間」は、サッカー史に残る数々の奇跡と悲劇を生み出してきました。
伝説の逆転劇①:カンプ・ノウの奇跡(1999年)
欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ決勝。マンチェスター・ユナイテッドはバイエルン・ミュンヘンに0-1でリードされたまま、アディショナルタイムに突入。誰もがバイエルンの優勝を確信したその時でした。アディショナルタイム1分に同点ゴール、さらにその2分後、信じられない逆転ゴールが突き刺さります。わずか数分で天国と地獄が入れ替わった、サッカー史最大の逆転劇として語り継がれています。
伝説の逆転劇②:アグエロォォォ!(2012年)
イングランド・プレミアリーグの最終節。マンチェスター・シティは、勝てば優勝という試合で、アディショナルタイムに2-2の同点に追いつくも、まだ足りない。ライバルチーム(マンチェスター・ユナイテッド)の試合は既に終わり、シティの優勝は絶望的に。しかし、表示されたアディショナルタイム5分が過ぎようとしていた93分20秒、FWアグエロが劇的な逆転ゴール!クラブに44年ぶりのリーグ優勝をもたらしたこの一撃は、実況の絶叫と共に伝説となりました。
忘れてはならない悲劇:ドーハの悲劇(1993年)
日本サッカーにとっても、アディショナルタイムは忘れられない記憶を刻んでいます。アメリカW杯出場をかけた最終予選のイラク戦。2-1でリードし、初のW杯出場が目前に迫った後半アディショナルタイムでした。イラクのコーナーキックからヘディングシュートを決められ、まさかの同点に。試合はこのまま終了し、日本のW杯出場の夢は、終了間際の数分で儚く散りました。
この時間は、希望にも絶望にもなりうるのです。
第5章:ただ待つだけじゃもったいない!観戦初心者が注目すべき「3つの視点」
スマホをいじるのはまだ早い!監督の表情と選手の動きで試合の結末が読めるかも
アディショナルタイムの仕組みとドラマ性を知ったあなたなら、もう試合終了間際をただ待つだけではもったいないと感じるはず。最後に、観戦がもっと深くなる「3つの視点」をご紹介します。
視点①【戦術】負けているチームの捨て身の攻撃「パワープレー」に注目!
1点ビハインドのチームは、残り時間で全てを懸けてきます。特徴的なのが「パワープレー」。守備の選手(特に長身の選手)を前線に上げて、ゴール前に人数をかけ、ロングボールを放り込んで強引にでもゴールを狙う戦術です。フォーメーションの変化や、なりふり構わぬ攻撃は、アディショナルタイムならではの見どころです。
視点②【頭脳戦】勝っているチームの華麗なる「時間稼ぎ」を見抜け!
逆に1点リードしているチームは、いかにして時間をうまく使うか、という頭脳戦を仕掛けます。
例えば、コーナーキックを得た際に、すぐにボールを蹴らずに相手選手と駆け引きをしながらコーナーフラッグ付近でボールをキープする「コーナーキープ(鳥かご)」。これは、相手にボールを渡さずに安全に時間を進める、非常にクレバーな戦術です。一見すると「ずるい」と感じるかもしれませんが、これも勝つための立派な戦略なのです。
視点③【人間ドラマ】監督の檄、選手の表情…ピッチ内外の感情を読み取れ!
ボールの行方だけでなく、ピッチ内外の「人間」に目を向けてみましょう。
- タッチライン際で声を枯らして指示を出す監督
- 最後の力を振り絞り、足がつりながらも走る選手
- ベンチで祈るように戦況を見つめる控え選手
- 一喜一憂し、チームを鼓舞し続けるサポーター
極限状態に置かれた人々の感情がむき出しになるこの時間帯は、サッカーというスポーツが持つ最高の人間ドラマが凝縮されています。
エンディング:アディショナルタイムを知れば、サッカーはもっと好きになる
さて、アディショナルタイムを巡る長い旅も、そろそろ終了の笛の時間です。
この記事で、あなたの「なぜ?」は解消されたでしょうか。
- なぜあるの? → プレーが止まった「消えた時間」を取り戻し、公平性を保つため。
- ロスタイムとの違いは? → 正式名称は「アディショナルタイム」。意味合いは同じ。
- どうやって決まるの? → 審判団が、交代やVARなどの空費時間を細かく計算している。
- なぜ面白い? → 最後の数分間に、数々の奇跡とドラマが生まれてきたから。
- どう見ればいい? → 戦術、頭脳戦、人間ドラマに注目すると、もっと楽しめる。
次にあなたがサッカーを観る時、第4の審判員が掲げる電光掲示板の数字は、もう単なる数字には見えないはずです。そこに込められた意味、これから始まるかもしれないドラマ、そして選手の想いを感じ取れるようになっているでしょう。
ようこそ、よりディープなサッカー観戦の世界へ。
この記事が、あなたのサッカーライフを少しでも豊かにするきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
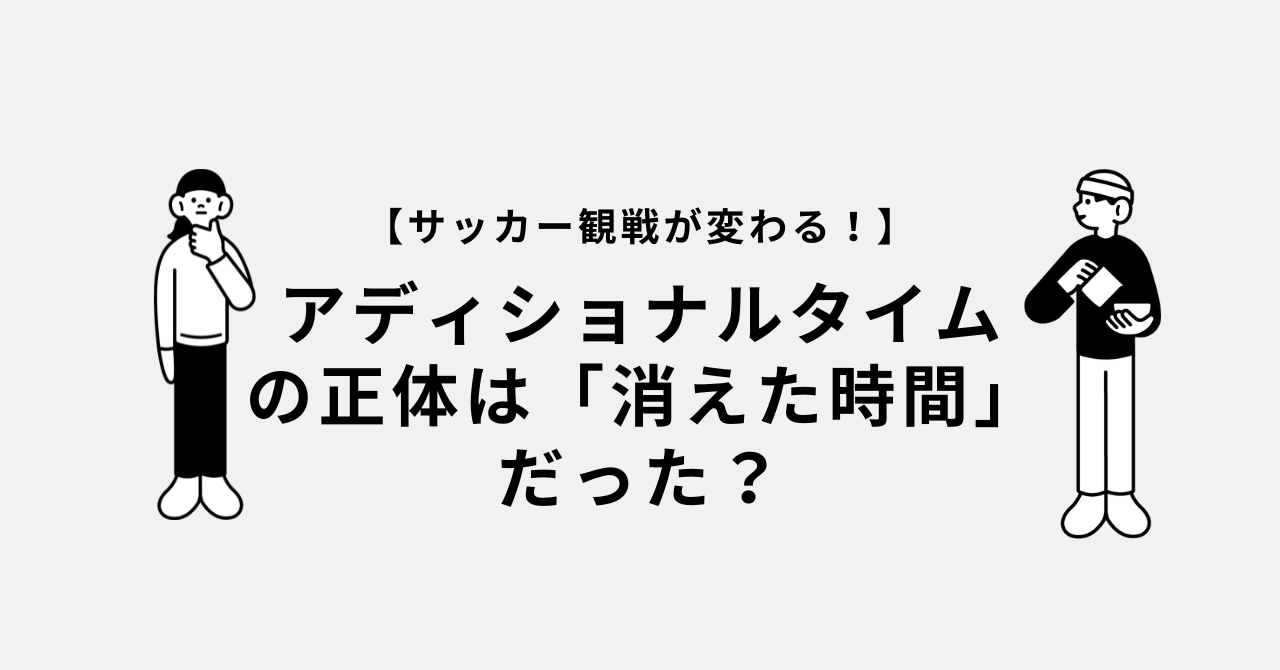
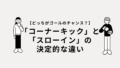

コメント